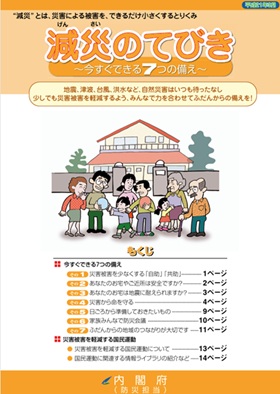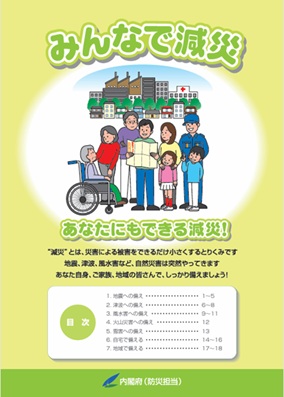男女共同参画 情報発信
すみれコラム「防災・減災」
地震、津波、台風など自然災害は思わぬときにやってきます。災害をなくすことはできませんが、被害を少しでも減らすことは今からでも取り組むことができます。災害被害をゼロに近づける備えは「防災」ですが、災害被害を最小限に抑える備えを「減災」と言います。つまり減災とは、災害や災害の被害は起こるものと前提して、災害が発生したときの被害を最小限にとどめるためにあらかじめ行う対策を指します。
私たち一人ひとりが日頃から具体的な行動(事前の備え)を考え、そのための行動を起こすことで、安全で安心して暮らしていける社会をつくっていくことができるのではないでしょうか。そのためには、まず、日常的にできることから取り組んでみましょう。
日頃から私たちにできる取り組みにはどのようなことがあるでしょうか。内閣府の「減災のてびき」では、日頃からできる「7つの備え」を紹介しています。
「減災のてびき」
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/gensai/tebiki.html
「みんなで減災」
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/gensai/gensai.html
「7つの備え」を分かりやすくまとめてみました。この機会に「7つの備え」を実践してみましょう。
1.普段からできることを考える
普段から「自分ができること」「家族でできること」「近所など周りと力を合わせてできること」などについて考え、災害に備えましょう。
2.お住まいの地域の安全性を確認する
防災マップやハザードマップをあらかじめ確認しておくことが重要です。防災マップは市町村役場や公民館での配布や、各自治体のホームページでの掲載を行っているため、普段から確認しておきましょう。
3.自宅を確認する
年月の経過やもともとの地盤によっても災害の影響度は異なるため、こまめな点検や整備がおすすめです。どのような家が地震に強いのかなど、基礎知識を身につけることも大切です。
4.正しい知識で身を守る
災害から命を守るには、その怖さを知った上で備えることが大切です。大地震のときには、多くの方が「家具類の転倒・落下」によって負傷してしまうことが判っています。家具を固定するなど「安全空間の確保」を見直してみましょう。水害や土砂災害の場合は、発生しやすい状況や前兆、発生後にはどのような二次災害が起こるかを知ることが重要です。最新の気象情報を入手することに努め、前ぶれや避難情報が出た場合にはすぐに避難を開始しましょう。
- 必需品や常備品を準備する
日ごろから防災グッズを携帯する「0次の備え」、災害発生直後にすぐに避難できるように非常持ち出し袋を準備する「1次の備え」、長期避難・在宅避難が必要となった場合に使う物資を準備する「2次の備え」をしておくことが大切です。
- 安否確認の方法を共有する
災害はいつどこで起きるかわからないため、1人のときに災害が起きたとしても落ち着いて行動できるよう、避難や安否の確認方法を日ごろから確認しておくことが大切です。決めた内容については家族で共有しましょう。
7.地域とのつながりを持つ
日ごろから近所の人と声をかけあうことで、いざというときに助け合える関係を築けるでしょう。また、周辺の家庭にお年寄りや障がいのある方がいるかを把握しておくことも重要です。